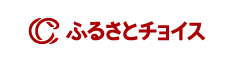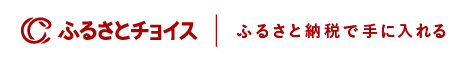もくじ
岐阜県高山市
岐阜県高山市は、東京都と同じくらいの面積を持つ”日本一面積が大きい市“です。
面積は大きいですが、その面積のほとんどが山。
高山市は約92%が森林の、全国で森林率が最も高い市でもあります。
(参考:高山市の概要 林野庁 都道府県別森林率)
この森林率から、どれだけ緑に囲まれているのかが伝わるかと思います。
市内から東には乗鞍岳を望む、盆地を中心とした山間部の市です。
飛騨地方
全国で一番広い森林面積を誇るのは北海道。ですが、岐阜県の森林率は高知県の84%に次ぐ81%の2位。
とは言っても、岐阜県南部の美濃地域は平野部も多く、ほとんど山間部なのが飛騨地域。
北は現在の飛騨市、西は世界遺産で有名な白川郷(白川村)。
一部西から東へまたがる中央部に高山市、南側には温泉で有名な下呂市。
この3市1村を合わせて「飛騨地域」です。
今でも「飛騨」という言われ方をしている理由の一つ。
同じ岐阜県内でも、気候風土が大きく違うこと。
積雪量、平均気温、生産物も違います。
そのため、「岐阜県」となったあとも、”飛騨”という名称は地域を指す言葉として使われています。
飛騨高山
そんな飛騨地域(飛騨地方)にある高山市。
旧市街地にある「古い町並み」は、江戸時代の面影を残す場所として、多くの観光客が訪れています。
日本酒や飛騨牛、地元の野菜など素材を活かしたグルメも充実しています。山岳由来の温泉も楽しめ、春と秋には豪華な祭り屋台と行列でにぎわう高山祭など。伝統文化も息づく町です。
”飛騨高山”と聞くと、「古い町並み」や「飛騨牛」、「高山ラーメン」などをまず思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
また、赤い中橋と祭り屋台、古い町並みが飛騨高山のメインイメージになっています。

木の文化と家具の産地
飛騨の匠
そんな高山市。
山に囲まれた内陸部ですが、飛騨地域には縄文時代から人が住んでいました。
縄文、弥生、古墳時代の遺跡もあり、”飛騨國”の名前は日本書紀、仁徳天皇の時代に名前が出てきます。
飛騨の名前で有名なのが”飛騨の匠”。
奈良時代から平安時代にかけて命じられた飛騨工(ひだのたくみ)制度のことから来ています。
この制度によって、木工従事者が都に行き、平城京や東大寺、大極殿など様々な造営に従事していました。
そのなかには優れた技術者もいたため、いつしか「飛騨工=優れた木工技術者」、”飛騨の匠”と呼ばれるようになったようです。
高山の歴史をもう少し知りたい方は、高山市のホームページで紹介されている、高山の歴史のページをどうぞ。
下記リンクからどうぞ。
山に囲まれていることからも想像出来るように、「木」と関わりの深い地域です。
地域の伝統工芸のなかにも、「一位一刀彫」や「飛騨春慶」など、木を使ったものもあります。
木の使用は時代と共に変化し、今では他の素材や輸入材に置き換わったりと、木の仕事も変化をし、飛騨地域の産業もその時代ごとに変化をしています。
ですが「木に関わる仕事」の姿は変わりながらも、その姿勢や精神は、近代化の中で家具づくりへと受け継がれています。
国産家具の産地
観光が高山の主なイメージ。
観光で来られる方の中には、知らない人もいますが、実は高山市は国産家具の3大産地の一つ。
福岡の大川家具、静岡の静岡家具に次ぐ規模の産地です。
「脚物(あしもの)」といわれる椅子やテーブルがメインで作られています。
産業を支える地元の大手家具メーカーから個人の小さな工房まで。
木工や山が好きで移住してきた方や地元の方など、木が好きな人も多いです。

飛騨の家具の始まり
明治末期。
日本に輸入された、ドイツ人のミハエル・トーネットが開発した曲木技術を使った最初の家具。
その優美さと優秀さから、この曲木椅子の製作が奨励され、国内産業として東京、大阪から始まります。
古来から薪や炭にされ家具等には使われていなかったブナ材が、曲木家具の材料として評価されるようになり、トーネット製造工程のように、木材産地に工場を設置し製材から製造を現地で行うために、曲木材を求めて秋田、そして飛騨へも技術と共に入ってきました。
こうして、元々木工文化のあった飛騨の地で近代的な家具づくりが始まったのです。
飛騨の匠や木工については、木工連合会の以下のリンクで詳しくご覧いただけます。
木製品を使う
直して使える長所
ふと、部屋を見回してください。
様々な電子機器に囲まれ、プラスチックや金属製品が増える中、木製の日用品は確実に減っています。
また、木製品を手にしても、
均一で整えられた木目模様が並ぶ店先。
「壊れたらすぐ買い替えればいい」という消費のリズムが、私たちを無意識に導いているのかもしれません。
ですが、「物を買う」事が、消費する事だけの時代から変わろうとしています。
手を入れ、直して使えるという事は、木製品の中でも特に無垢の木の製品の最大の長所です。
オイルを塗ることで艶を取り戻す木肌は、年月と共に深みを増します。
子どもの成長を記録する机。
目立つ凹みや傷は直しながらも、重ねる記憶と時間。
10年後も20年後も、家族の歴史を刻み続けるダイニングテーブル。
こうした「一生もの」を選ぶことが、環境負荷を減らす選択ではないでしょうか。
消費ではない「物を大切にして使う」ことに、心のゆとりや豊かさがあります。
ふるさと納税を例に
高山市でも「ふるさと納税」を受け付けています。
その中でも人気なのは、やはり観光でもイメージの強い「飛騨牛」。
他にも、地酒や地元の野菜や、ラーメン、トマトやりんごに乳製品など。食品も多いなか、雑貨や家具・インテリア、民芸・工芸の多くが「木」を使っており、ほとんどが木製品です。
市内大手の家具メーカー品から、個人の作家さんの小物まで様々。
小さなお子さま用の木のおもちゃから、使い続けることができる家具までさまざまな木の製品があります。
ご興味ある方は以下の各リンクからご覧いただけます。
雉子舎の製品も、ふるさと納税でご寄付の際にお選びいただけます。
無垢の木の製品は欲しいけど、椅子やテーブルはハードルが高いと感じる方。
そういった方にお勧めなのは、コースター等の小物から、スツール、ダイニングチェア、鏡やテーブルなど。
扱いやすい小さなものからいかがでしょうか。
座りやすい形状に座刳り(ザグリ)をしてあるム-ンスツール挽脚は、体にフィットする座り心地で、背もたれがないことで空間を広く使える椅子としてもお使いいただけます。
飛騨の家具Ⓡを使う
木と共に、自然と共に。
あなたと共に紡ぐ。
「飛騨の家具」という選択。
飛騨の家具には10年保証がついています。
修理可能な構造が大量消費への抗いとなる。
長く使うほどに深まる風合い。
手をかけ、時間を重ね、世代を超えて受け継がれる、そのこと自体を美しく感じます。
“いいものを、丁寧に選んで暮らす”という生き方が、そこにあります。
1300年の技と今を生きる感性によって、静かに、確かな存在感をもって生まれた家具に、その木目に刻まれる人の営み、記憶こそ、何より尊い財産ではないでしょうか。
「雉子舎(